食べコレ!は、たやすく生まれてきた店ではない。いや、それどころかかなりの難産だった。一時は誕生すら危ぶまれ、僕たちは皆、口には出さないにせよ、不幸な結末の予感を胸に忍ばせながら絶望的な努力を続けていた。つわりがひどく、危険は母体であるまいど屋にも及んだ。それは僕たちにとって、全く予想外のことだった。本来であれば、今年の春には、店は取り立てて大きな問題もなく完成し、今回のレポートとはかなり雰囲気を異にする晴れやかな特集を皆さんにお届けする予定だったのだ。まるで舗装された直線道路をオートクルーズのモードでドライブするみたいに、僕たちはほとんど苦労をすることもなく目的地に到着するはずだったのだ。だが、実際に僕たちが歩んだ道はまるで違ったものだった。道路はぬかるみ、何度も車輪を取られ、そのたびに僕たちは立往生を強いられた。思ってもみなかった障害がまるでまいど屋の意思を試すかのように次々と現れ、メンバーの気力と体力を奪っていった。途中で何人かの脱落者まで出た。しまいには僕たちが進んでいるその道が、本当に目的地に向かっているのかさえ分からなくなった。だから最終的に店のオープンが決まった時も、残ったメンバーの誰一人として、食べコレ!が当初目指した場所に到着しているのかどうか確信が持てなかった。喜びというよりはホッとした安堵の方が大きかった。僕たちは皆、放心したように互いの顔を見つめ合い、それから特に感慨もなく開店の日の印をカレンダーに書き込んだ。
通販サイトの特集で、これから書くようなことなどは、本当はお話ししない方がいいことくらいはわかっている。だが、あえて皆さんには正直に打ち明けよう。そうすることで、僕たちは僕たちが抱いている想いをなんとか皆さんと共有できそうな気がするし、それによってある意味で、崩壊寸前から生還したこのプロジェクトのように、僕たち自身も救われるように思えるからだ。僕たちの中には、未だ複雑な感情が渦巻いている。烙印のように刻み込まれた深い傷跡が、どうにかして癒されることを求めている。僕たちは、僕たち自身が救済されるためにも、この物語を物語らなければならないのだ。そんな風に考えながら、この後の続きを書いていく。読者の皆さんにとってはさほど興味をひかれる内容ではないかもしれないが、しばらくお付き合いいただきたい。見えない檻のようなものの中に知らぬ間に閉じ込められ、今ももがき続けている僕たちを助けると思って。
通販サイトの特集で、これから書くようなことなどは、本当はお話ししない方がいいことくらいはわかっている。だが、あえて皆さんには正直に打ち明けよう。そうすることで、僕たちは僕たちが抱いている想いをなんとか皆さんと共有できそうな気がするし、それによってある意味で、崩壊寸前から生還したこのプロジェクトのように、僕たち自身も救われるように思えるからだ。僕たちの中には、未だ複雑な感情が渦巻いている。烙印のように刻み込まれた深い傷跡が、どうにかして癒されることを求めている。僕たちは、僕たち自身が救済されるためにも、この物語を物語らなければならないのだ。そんな風に考えながら、この後の続きを書いていく。読者の皆さんにとってはさほど興味をひかれる内容ではないかもしれないが、しばらくお付き合いいただきたい。見えない檻のようなものの中に知らぬ間に閉じ込められ、今ももがき続けている僕たちを助けると思って。
チャプター2

食べコレ!立ち上げスタッフの北平さん
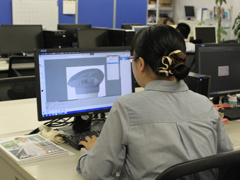
商品画像を加工するスタッフ
食べコレ!のプロジェクトが正式にスタートした時、僕たちは自信満々だった。過去二度ほどお店を作ってきた僕たちにとって、それはとても簡単なことだとまでは言わないものの、割りとスムースに準備を進めていける案件だと思ったのだ。これまでの経験が、僕たちに自信を与えていた。去年の初め、スタッフが集まってささやかに開いたキックオフの会合では、誰もがそれぞれの希望を語っていた。多少のアルコールが入っていたこともあり、僕たちのテーブルの上を忙しく飛び交ったそれらの夢は、どれもいともたやすく実現しそうに思われた。僕たちは笑顔を浮かべながら、大いなる気負いと使命感を含んだ言葉を吐き続けた。僕たちは万能で、他者に対して寛容だった。そしてとても幸せだった。
どこでどう歯車が狂ってしまったのだろう。僕たちが歩んできた道を振り返りながら今もときどき考えてみるのだが、どうしても特定のポイントが思いつけない。たぶん、僕たちは思い上がっていたのだろう。何でもできると信じ込み、理想と現実の区別がつかなくなってしまっていたのだ。たとえ誰かが何か違うんじゃないかと気付いたとしても、そうした冷静さは僕たち全体を包んでいた熱狂の中にたちまち掻き消されてしまう。そして全員で同じゴールに向かうふりをしながら、実際はめいめいが、てんでんばらばらの方向を向いてしゃにむに足を動かそうとしていたのだ。
例えば・・・
「事務コレ!で蓄積したノウハウを活かして、飲食店バージョンに落とし込めばすべてうまくいく。実績もあるし、マニュアルも兼用できる。姉妹サイトとしての統一感もあり、グループ全体の訴求力が上がるはずだ」。
「飲食業のひとたちが、事務コレ!と同じだから使いやすいと評価してくれるとは思えない。そもそも、彼らは事務コレ!なんて全く知らないはずだよ。それよりは、これまでにない切り口で行きたい。シーンで見せたほうがお客さまもイメージしやすく、選びやすいんじゃないか」。
「サイトの入口はコーディネートしたセットアップ画像にすべき。まずスタイルで選んで、それから各単品に飛ぶという方式で」。
「いや、もっと簡潔にした方がいい。選びやすい、買いやすいが通販の基本なのだから」。
そんな風に議論はかみ合わず、時間だけがいたずらに空費された。その間、システム構築やデータ入力は着々と進んでいったが、肝心の「どう見せるか」「どう区分けするか」がいつまでも決まらなかった。
一番の問題は、誰がリーダーシップをとっているのか、全体としてのはっきりした合意がないことだった。それぞれのメンバーのモチベーションは非常に高かったのだが、全員自分が主導権を握っていると思い込んでいた。誰かが開発に自分のアイデアを投げると、次の日には違う誰かがそれとは両立できるはずのない別のアイデアを持ち出してきた。当然、開発陣は途方に暮れて立ち往生してしまう。それでもどちらの顔も立てようと無理に頑張りすぎるものだから、いつの間にか店は何やらわけのわからない、奇形じみた風貌を帯び始めていった。暴走を続けるプロジェクトを整理し直さなければならないことは、既に誰の目にも明らかだった。最早一刻の猶予もなかった。
当時のことを、スタッフの落合さんはこう話す。「最初はよかったんだけど、だんだん、他のスタッフが信じられなくなってきたんだよね。ようやくみんなの意見がまとまったと思ってホッとしていると、知らないところで打ち合わせになかった別の動きが持ち上がる。衝突、理不尽、疑心暗鬼の毎日が続いて投げやりになりそうな自分と闘ってた。どうしてそうなるのか、全く分からなかった」。
過労とストレスで体調不良になるスタッフがぽつぽつと出始めた。軽い鬱状態になって出社できなくなる者もいた。この時点で全員が共有しつつあった思いはただ一つ、これ以上続けてもきっと結果は出せないだろうということだけだ。そしてついに決断が下された。まいど屋は、このプロジェクトのリーダーとして、外部から新しい人材を迎え入れたのだ。既存のメンバーから一人を選ぶことは、プロジェクトの空中分解につながりかねなかったからだ。
着任したのは、山岸さんという元エンジニアの男性だった。山岸さんの動きは素早かった。店のコンセプトを彼独自のアイデアで新たに設計し直し、メンバーにその通り動くよう通達した。独裁が始まった。過去に語られた夢の数々は、容赦なく全てゴミ箱に放り込まれた。古くからのメンバーが何人か去って行った。残ったメンバーもフラストレーションをため込んだ。それでも山岸さんは動じなかった。そしてプロジェクトの最終段階にさしかかり、店のオープンが視野に入り始めたとき、山岸さんは彼が現れた時と同じように、突然辞任してまいど屋を去った。そのころは徐々に彼とメンバーの間の距離も縮まってきており、これからいい関係が築けそうな気がしていただけに意外だった。俺は差し違えたんだよ、と山岸さんは言ってにっこりと笑った。さみしそうな笑顔だった。「もう俺がいなくても大丈夫だろう。開店までもう少しだ。みんな、頑張ってくれよ」。
山岸さんがいなくなった後も、僕たちは彼が残したコンセプトに沿って開発を続けた。もう誰もわがままを言ったり、自分の意見を押し付けようとする者はいなかった。ただ、黙々と作業を続け、店はようやくオープンすることになった。達成感はどこにも見当たらず、代わりに僕たちの胸にはホロ苦い思いが満ちていた。食べコレ!と引き換えに、僕たちはいろいろなものを失ってしまったのだ。まいど屋にとって、犠牲は痛恨ともいえるほど、あまりにも大きすぎた。それでも僕たちは思う。僕たちにはやはり、食べコレ!が必要だったのだと。もう一度あのキックオフの日に戻れるとしても、僕たちはやはり同じように、食べコレ!の夢を語り合うだろう。近づくだけで火傷をするくらい熱く、他人に笑われるほど青臭く、周囲の意見など考えることもせず、それでいて全く自分たちの能力をわかっていない、恐れを知らない子供のように無邪気に、ナイーブに。
「長い夢を見ていたような感じです。それもとびきりイヤな悪夢ね。今はチームワークもよくなり、昔のような一体感が感じられるようになってきたので、本当の勝負はこれからです」と北平さんはまっすぐ前を見て言う。僕たちは遺された食べコレ!を大事に育てながら、失ってしまった大切なものをこれからゆっくりと時間をかけて取り戻していこうと思う。この長い物語に付き合ってくれた読者の皆さんと一緒に。
どこでどう歯車が狂ってしまったのだろう。僕たちが歩んできた道を振り返りながら今もときどき考えてみるのだが、どうしても特定のポイントが思いつけない。たぶん、僕たちは思い上がっていたのだろう。何でもできると信じ込み、理想と現実の区別がつかなくなってしまっていたのだ。たとえ誰かが何か違うんじゃないかと気付いたとしても、そうした冷静さは僕たち全体を包んでいた熱狂の中にたちまち掻き消されてしまう。そして全員で同じゴールに向かうふりをしながら、実際はめいめいが、てんでんばらばらの方向を向いてしゃにむに足を動かそうとしていたのだ。
例えば・・・
「事務コレ!で蓄積したノウハウを活かして、飲食店バージョンに落とし込めばすべてうまくいく。実績もあるし、マニュアルも兼用できる。姉妹サイトとしての統一感もあり、グループ全体の訴求力が上がるはずだ」。
「飲食業のひとたちが、事務コレ!と同じだから使いやすいと評価してくれるとは思えない。そもそも、彼らは事務コレ!なんて全く知らないはずだよ。それよりは、これまでにない切り口で行きたい。シーンで見せたほうがお客さまもイメージしやすく、選びやすいんじゃないか」。
「サイトの入口はコーディネートしたセットアップ画像にすべき。まずスタイルで選んで、それから各単品に飛ぶという方式で」。
「いや、もっと簡潔にした方がいい。選びやすい、買いやすいが通販の基本なのだから」。
そんな風に議論はかみ合わず、時間だけがいたずらに空費された。その間、システム構築やデータ入力は着々と進んでいったが、肝心の「どう見せるか」「どう区分けするか」がいつまでも決まらなかった。
一番の問題は、誰がリーダーシップをとっているのか、全体としてのはっきりした合意がないことだった。それぞれのメンバーのモチベーションは非常に高かったのだが、全員自分が主導権を握っていると思い込んでいた。誰かが開発に自分のアイデアを投げると、次の日には違う誰かがそれとは両立できるはずのない別のアイデアを持ち出してきた。当然、開発陣は途方に暮れて立ち往生してしまう。それでもどちらの顔も立てようと無理に頑張りすぎるものだから、いつの間にか店は何やらわけのわからない、奇形じみた風貌を帯び始めていった。暴走を続けるプロジェクトを整理し直さなければならないことは、既に誰の目にも明らかだった。最早一刻の猶予もなかった。
当時のことを、スタッフの落合さんはこう話す。「最初はよかったんだけど、だんだん、他のスタッフが信じられなくなってきたんだよね。ようやくみんなの意見がまとまったと思ってホッとしていると、知らないところで打ち合わせになかった別の動きが持ち上がる。衝突、理不尽、疑心暗鬼の毎日が続いて投げやりになりそうな自分と闘ってた。どうしてそうなるのか、全く分からなかった」。
過労とストレスで体調不良になるスタッフがぽつぽつと出始めた。軽い鬱状態になって出社できなくなる者もいた。この時点で全員が共有しつつあった思いはただ一つ、これ以上続けてもきっと結果は出せないだろうということだけだ。そしてついに決断が下された。まいど屋は、このプロジェクトのリーダーとして、外部から新しい人材を迎え入れたのだ。既存のメンバーから一人を選ぶことは、プロジェクトの空中分解につながりかねなかったからだ。
着任したのは、山岸さんという元エンジニアの男性だった。山岸さんの動きは素早かった。店のコンセプトを彼独自のアイデアで新たに設計し直し、メンバーにその通り動くよう通達した。独裁が始まった。過去に語られた夢の数々は、容赦なく全てゴミ箱に放り込まれた。古くからのメンバーが何人か去って行った。残ったメンバーもフラストレーションをため込んだ。それでも山岸さんは動じなかった。そしてプロジェクトの最終段階にさしかかり、店のオープンが視野に入り始めたとき、山岸さんは彼が現れた時と同じように、突然辞任してまいど屋を去った。そのころは徐々に彼とメンバーの間の距離も縮まってきており、これからいい関係が築けそうな気がしていただけに意外だった。俺は差し違えたんだよ、と山岸さんは言ってにっこりと笑った。さみしそうな笑顔だった。「もう俺がいなくても大丈夫だろう。開店までもう少しだ。みんな、頑張ってくれよ」。
山岸さんがいなくなった後も、僕たちは彼が残したコンセプトに沿って開発を続けた。もう誰もわがままを言ったり、自分の意見を押し付けようとする者はいなかった。ただ、黙々と作業を続け、店はようやくオープンすることになった。達成感はどこにも見当たらず、代わりに僕たちの胸にはホロ苦い思いが満ちていた。食べコレ!と引き換えに、僕たちはいろいろなものを失ってしまったのだ。まいど屋にとって、犠牲は痛恨ともいえるほど、あまりにも大きすぎた。それでも僕たちは思う。僕たちにはやはり、食べコレ!が必要だったのだと。もう一度あのキックオフの日に戻れるとしても、僕たちはやはり同じように、食べコレ!の夢を語り合うだろう。近づくだけで火傷をするくらい熱く、他人に笑われるほど青臭く、周囲の意見など考えることもせず、それでいて全く自分たちの能力をわかっていない、恐れを知らない子供のように無邪気に、ナイーブに。
「長い夢を見ていたような感じです。それもとびきりイヤな悪夢ね。今はチームワークもよくなり、昔のような一体感が感じられるようになってきたので、本当の勝負はこれからです」と北平さんはまっすぐ前を見て言う。僕たちは遺された食べコレ!を大事に育てながら、失ってしまった大切なものをこれからゆっくりと時間をかけて取り戻していこうと思う。この長い物語に付き合ってくれた読者の皆さんと一緒に。

データ入力に追い込みをかける食べコレ!チーム
|

